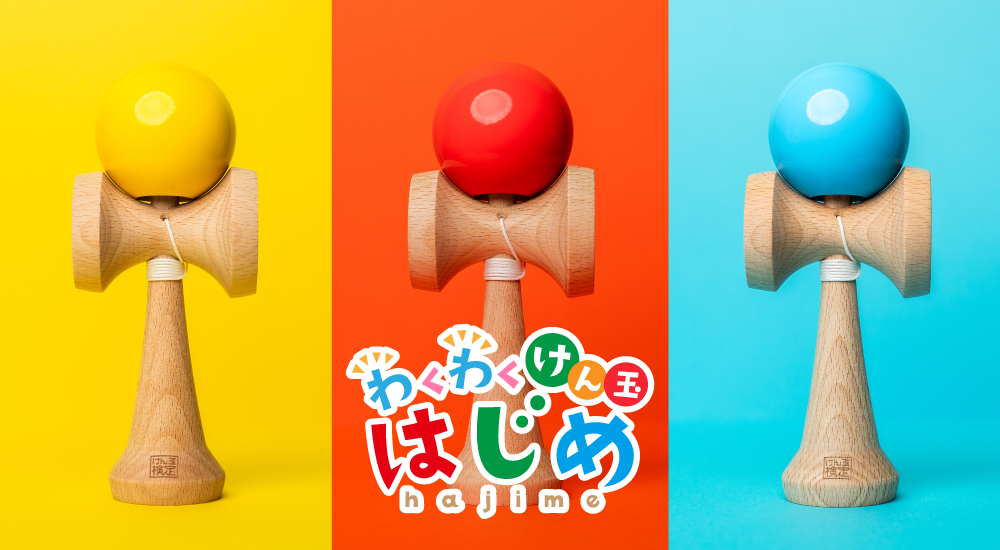China Kendama Openと北京でのけん玉交流
2025年7月26日(土)、27日(日)、中国の深セン市内で開催された China Kendama Open(CKO) と、その後の北京でのけん玉交流のため、約10日間中国へ行ってきました。
昨年は直前にケガをして訪問がキャンセルとなったため、実に6年ぶりの訪問でした。
CKOは、2019年から開催されている大会で、中国国内のトッププレーヤーを中心に盛り上がり、今年は香港、マカオ、そして日本からも精鋭の選手が集う大きなイベントでした。
私は審判団の一員としての参加でしたが、130名以上の出場者と、会場全体を包み込むような熱気と歓声は、今も耳と心に残っています。
今年、GLOKENでは、大正時代に現在のけん玉の元祖「日月ボール」を考案した江草濱次さんの足跡をたどる活動に大きな進展が見られました。もし、けん玉考案者の江草濱次さんが、現在のように世界中でけん玉が愛され、国境を越えて人が集まり、大会や交流が盛んに行われている姿を見たら…という事に、思いを馳せずにはいられません。
自分の手で生み出したものが、時代や場所を超えて人々に影響を与え続ける——それは発明家、あるいは新しい道を切り開く人間にとって、最高の誉れに違いありません。
この10数年間、世界のけん玉シーンを見続けていますが、感じる事は、良いモノがあるだけでは自然には広まらないという事。大きなけん玉シーンが存在する場所には、必ず、けん玉を広めたいという強い情熱を持った「人」が必要で、練習会やショップのような「集まる場所」があって、「新しい層に広める仕組み」が存在し、「イベント」や「大会」という舞台が整ってはじめて、コミュニティは力強く育つのだと思います。
日本でも、大正から昭和にかけて「日月ボール」の大ブームが起こりましたが、その草創期には江草家の方々が全国で、神社やお寺で大会を開きながら、地道に宣伝と普及活動を行っていた歴史がありました。
近年でも、けん玉ブームが巻き起こったハワイ、シンガポール、イスラエル、ルーマニアなど、世界各地の様子を見聞きしてきた中でも、この構造は今も昔も変わらない真実だと感じます。
今回の中国でも、同じことが見えます。
6回目のCKOイベントを作り上げた運営スタッフの皆さんの熱量には、何度も胸を打たれました。けん玉への深い愛情、プレーヤーへの細やかな心配り、そして未来を見据えた行動力。例えば、ステージ上では中国最高レベルの大会が繰り広げられている一方、ロビーではスタッフが初心者向けのけん玉教室を開き、小さな子どもたちに手取り足取りけん玉を教えている光景がありました。そして、行政を巻き込み、表彰式に子どもの教育、育成に関わる行政部署の方が来たり、大会の見学に招待していたりと、新たな取り組みを進めていました。
大ブームになるかどうかは分かりませんが、今後も着実に、中国においてけん玉の輪が広がっていくことを期待しています。
(窪田)
大会結果は、GLOKENインスタ(@gloken_dama)に掲載しています!
https://www.instagram.com/gloken_dama/